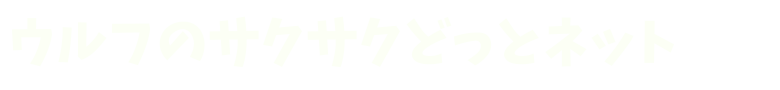2025年10月、世界は日本人研究者2名のノーベル賞受賞という喜びに包まれました。医学部門では Shimon Sakaguchi(坂口–志文/阪口志文という表記も見られます) が選ばれ、化学部門では Susumu Kitagawa(北川進とは異なり、英語表記 Kitagawa) が受賞。日本の科学技術の成熟と底力を改めて象徴する出来事です。
以下では、二人のプロフィールと研究内容を、小学生にも伝わるようにやさしく解説しつつ、授賞式のスケジュール、そして“これからの日本”を希望とともに描きます。
Shimon Sakaguchi(医学賞)とはどんな人?
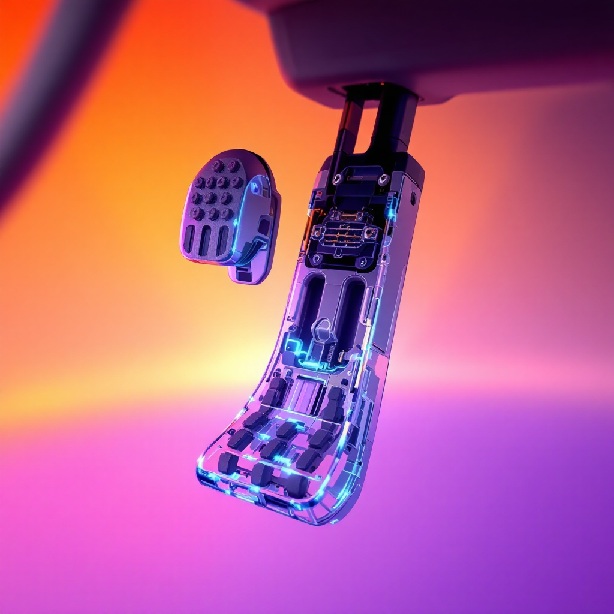
生年月日・出身・所属
Shimon Sakaguchi は1951年1月19日、滋賀県長浜市出身。現在は大阪大学を拠点とし、かつては京都大学でも研究を重ねてきた免疫学者です。
歩み・モチベーション
若い頃から“なぜ体の免疫が誤って自分を攻撃しないか”という問いを抱えていた Sakaguchi。1990年代から、従来の考え方を越える“抑制機構”の存在に着目し、数々の実験を重ねてきました。
研究テーマをやさしく説明:制御性T細胞(Regulatory T cells)
免疫とは、ウイルスや細菌を攻撃する“兵隊”のような細胞たちの働きですが、もしこれが“味方”まで攻撃してしまったら体が壊れてしまいます。Sakaguchi たちは、制御性T細胞(Treg 細胞)という“ブレーキ役”細胞を発見しました。これは、免疫の兵隊が暴走しないようにブレーキをかけ、体を守る仕組みです。具体的には FOXP3 という遺伝子がこの制御細胞に鍵を握ることを見出しました。
たとえば、自動車で言えばアクセルが免疫攻撃、ブレーキが制御性T細胞、と考えるとわかりやすいでしょう。
功績・影響
彼の発見は、自己免疫疾患(体が自分を攻撃してしまう病気)や移植医療、がん免疫療法の分野で新しい治療の道を拓くものです。現在でも、制御性T細胞を活用した治療法が臨床試験段階に入っています。
 | 免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか (ブルーバックス) [ 坂口 志文 ] 価格:1210円 |
Susumu Kitagawa(化学賞)とはどんな人?

生年月日・出身・所属
Susumu Kitagawa は1951年7月4日、京都生まれ。京都大学で学び、現在も京都大学を拠点に研究を続けています。
2025年の化学賞受賞により、日本が化学分野で世界に輝く機会が再び訪れました。
研究テーマ:金属有機構造体(MOF)をやさしく
MOF(Metal-Organic Frameworks)は、金属イオンと有機分子を“結びつけて”できる“網目構造”のようなものです。中には空洞があって、ガスが入り込んだり、分子が行き来したりする構造を持ちます。
例えるなら:“分子のための部屋”です。空気中の水を集めたり、有害ガスを捕まえたり、環境浄化や燃料貯蔵に使えるような性質を持つ構造です。
Kitagawa の功績は、このMOFを“可動性を持たせてガスの出入りを制御できる構造”を設計したことです。
 | 価格:59400円 |
応用例・未来への展望
- 砂漠の空気から水を取り出す
- 二酸化炭素を吸着して温暖化ガスを減らす
- 医薬品輸送や水浄化フィルター
- 高性能バッテリーの材料
こうした技術が社会インフラや環境技術に結びつく可能性があります。
 | ナノサイエンスが作る多孔性材料 普及版[本/雑誌] (〔CMCテクニカルライブラリー〕 349 新材料・新素材シリーズ) (単行本・ムック) / 北川進 価格:3740円 |
授賞式スケジュール・式典概要
ノーベル賞の公式授賞式は 12月10日(アルフレッド・ノーベルの命日)にストックホルムで行われます。
医学賞・化学賞ともに、12月10日の式典では王室出席・メダル授与・晩餐会が伝統的に行われます。
日本からは受賞者およびアカデミック関係者、報道関係者が式典に出席する見込み。臨場感ある映像中継や国内報道番組も予定されるでしょう。
授賞式直前には、受賞者のストックホルム到着や各国大使館での歓迎行事、レクチャーイベントが前後に展開されます。
日本の技術と研究、“次のノーベル賞候補”たち

材料科学・環境技術分野
日本には空気浄化材料、次世代触媒材料、ナノ物質分野の研究者が多くいます。特に MOF をさらに発展させた応用研究に注目が集まります。
免疫・再生医療分野
制御性T細胞の応用から派生する、自己免疫疾患治療や移植医療、がん免疫療法の研究は日本国内でも盛んです。
若手研究者、バイオベンチャー、医学系研究所の連携に期待がかかります。
AI融合医療・バイオインフォマティクス
遺伝情報・個別化医療・創薬・シミュレーション研究。次のノーベル賞を視野に入れた研究テーマとして、クロス領域融合が鍵です。
未来への希望

この二人の受賞は、日本科学界にとっての新しい灯火です。「日本はもう先端を走れない」と言われた時代もありましたが、ここに来て再び世界の舞台に立つ力があることを証明してくれました。技術だけでなく「問い」を持つ研究、翻訳力・発信力を持つ人材育成、日本独自の視点を守る文化資本——これらが揃えば、次の世代がノーベル賞を日本語作家・日本人研究者として勝ち取る日も遠くないと思います。
科学も文学も、問う人がその土地を映す光を持ちます。研究に携わる方々も、読む・書く・考える人々も、この受賞の光を胸に、少し肩を正して明日へ歩みたいと思います。