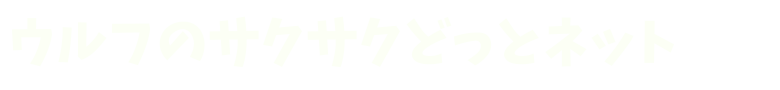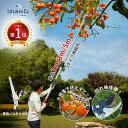本記事は安全啓発を目的に作成しています。最新の出没情報・立入規制は 自治体の公式発表を必ずご確認ください。危険を感じたら直ちに110番か自治体へ通報してください。
1. クマ出没が止まらない—2025年秋、日本各地で警戒続く
2025年の秋、日本各地でクマの出没が相次いでいます。北海道から東北、北陸、関東の山間部に至るまで、ニュースで「民家の軒先にクマ」「通学路に出没」という報道を見ない日はありません。
環境省の調査によると、ここ数年でツキノワグマ・ヒグマの目撃件数は過去最多レベルに増加しており、人里に現れる“人慣れしたクマ”が増えているのが特徴です。
主な原因は以下の3つとされています。
- ドングリやクルミなどの「木の実」が不作(気候変動や台風による影響)
- 山林の管理放棄で「人と山の境界」があいまいになった
- クマの個体数そのものが増えている
山だけではなく、住宅街や通学路でもクマが現れる時代。私たち一人ひとりが、遭遇しない行動習慣を持つことが命を守る第一歩です。

2. クマは本来「人を襲わない」—しかし条件が揃うと危険
クマは基本的に臆病な動物で、人間の気配を感じると自ら離れることがほとんどです。
しかし「子連れ」「空腹」「驚かされた」などの条件が重なると、防衛本能から攻撃に転じることがあります。
特に危険なのは次のような状況です。
- 子グマを連れた母グマ(最も危険)
- 餌を見つけている最中(食事中)
- 夕暮れ〜夜明けなど、視界の悪い時間帯
実際に、急斜面の登山道や山菜採り中の遭遇が多く、「先に気づくこと」こそが最大の防御です。
3. 出没リスクを下げる!日常でできる5つの対策
人里にクマを呼び込まないためには、日々の暮らしからできる工夫が大切です。
- ゴミを屋外に出さない
特に生ゴミや魚の骨など、匂いの強いものはクマを引き寄せます。密閉容器や冷凍保管が有効です。 - 果樹の管理を徹底
落ちた果実をそのまま放置すると、クマが夜間にやってきます。早めに拾いましょう。
最近のテレビの情報番組では、今年豊作となった柿の実を、気に登って食べるという情報があり ました。クマにとっては甘い柿も渋柿も関係ないそうで、両方関係なく食べるそうです。
クマの出没地域にお住いの方は、果樹の早め収穫も検討した方が良さそうです。 - 外飼いのペットの餌は残さない
猫や犬の餌もクマを誘引します。また、外飼いの犬がクマに連れ去られたという報道も記憶に新しいところ。出没情報のある地域のペットは要注意です。
- 自治体の情報を常にチェック
「出没マップ」やLINE通知を活用して最新情報を入手。 - 通勤・通学時間帯を少しずらす
日の出直後や日没時はクマの活動時間です。早朝のジョギングなどは控えましょう。
4. 山・キャンプ・ハイキングでの安全行動
登山やトレッキングでは「遭遇しない準備」が最も重要です。
- 熊鈴を携帯する:音で人間の存在を知らせます。学習能力の高い熊だと、食べ物を持っている、あるいは、「食べ物≒人間」と判断し逆に呼んでしまうと言う人もいます。地域性や熊の種類にもよると思いますので、情報収集は欠かせません。
- 複数人で行動する:単独行動は避けましょう。
- 視界の悪い藪には入らない。見えない場所では声を出すことも有効です。
- 食べ物の管理を徹底。テント内にお菓子を置かない。
- 夜間の移動は避ける。
 | プラスリブ 忌避剤 撃退クマ 5個入 忌避剤 害獣対策 防獣 価格:2200円 |
5. 万が一出会ってしまったときの行動
クマに遭遇してしまったとき、最も危険なのは「驚いて走ること」です。
背を向けると追いかけられる危険があります。距離別に行動を整理します。
- 遠くに見えた場合:落ち着いてゆっくり後退。
- 近距離で鉢合わせ:静かに声をかけながら後ずさり。
- 威嚇された場合:手を広げて大きく見せ、静かにその場を離れます。
- 攻撃された場合:ツキノワグマなら「うつ伏せで首を守る」。
ヒグマなら反撃せず、地面に伏せて動かないのが基本。
「死んだふり」は万能ではありませんが、最後の手段として覚えておきましょう。
6. クマ対策グッズの選び方
市販されている熊対策グッズは多様です。おすすめは以下の3つです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 熊撃退スプレー | トウガラシ成分でクマを退ける。登山口や林道でも携帯推奨。 |
| 熊鈴 | 軽量・安価で効果的。登山リュックの外側に装着。 |
| LEDライト | 夜間に人の存在を知らせる補助アイテム。 |

7. クマを見たらどうする?通報の流れ
- 警察(110)または自治体に連絡
- 写真を撮るよりも、自分の安全を優先
- SNS投稿は控える(人が集まって危険)
- 通報内容:場所・時間・クマの大きさ・行動を簡潔に
行政は出没パトロールや捕獲の判断を行います。
個人で「駆除」するのは違法になる可能性があるため絶対にやめましょう。
8. (興味ある方向け)狩猟免許の取得の流れ/注意点 — 日本で合法的に狩猟を行うには
狩猟は法律で厳格に管理されています。個人で“クマを駆除する”ことは自治体の判断と許可が必要です(行政が被害対策として行う場合が一般)。個人が狩猟を考える場合は、まず狩猟免許の取得が必要です。手順の概略をわかりやすく説明します(詳細はお住まいの都道府県へ確認してください)。
ステップ1:対象の免許種類を確認する
- 狩猟免許は猟具別に4種(第一種銃猟免許=散弾銃等、第二種銃猟=空気銃、わな猟免許、網猟免許)に分かれます。銃を扱うには別途、銃砲所持許可(警察)の手続きが必要。
ステップ2:都道府県窓口に申し込む
- 申し込み・試験日程・場所は都道府県担当窓口が告知します(環境省の都道府県一覧も参照可能)。申請書類・手数料は各都道府県で異なるので確認。
ステップ3:試験の3本立てを受ける
- 知識試験(筆記):三肢択一式、30問、90分。合格は概ね70%以上(21問正解が目安)。法令、鳥獣の判別、猟具の扱い等が出題されます。
- 適性試験:視力・聴力などの基準を満たすかを確認。
- 技能(実技)試験:猟具の取扱いや鳥獣判別の実技など、区分に応じた実技。技能も70%前後を基準に合否が決まります。
ステップ4:合格後の手続き
- 合格通知の後、狩猟者登録(都道府県)等を経て免許交付。銃猟の場合は銃砲所持許可の申請が別途必要(警察)。詳細は各都道府県に問い合わせてください。
注意点(必ず守ること)
実務的なスキルと安全教育が必須:猟具の扱い、法令遵守、安全管理の習熟が求められます。
個人的な駆除行為は原則不可:クマの捕獲・駆除は自治体の要請や許可に基づいて行われます。被害防止目的でも、勝手な行動は法律違反になるリスクがあります。
筆者の友人が、数年前に狩猟の免許(第一種銃猟免許)を取得したとのことで、そんな趣味があったのかと話を聴いたことがありました。彼は千葉県の某市役所職員ですが、市内の山林近くの農家や田畑でイノシシの被害がきっかけだったそうです。
行政から猟友会に依頼をすると、来て下さる方々が、ご年配ばかりだったとか。後進が育っていないという話を聴き、それならばと、狩猟免許取得の決心をしたそうです。
数年前に免許はとったものの、本人曰く、「まだまだ修行の身」とのこと。狩猟後の捌きについても勉強中で、「おじいちゃんたちに教わってる」と。
免許を取ったとしても、技術を習得するのに年数を要します。
銃などの保管についても大きな責任とリスクが伴いますので、覚悟を持って免許取得をご検討ください。

9. まとめ
クマは強く怖い相手ですが、基本は「出会わないこと」が最優先です。地域で誘引物を減らし、日常の管理を徹底し、山に入るときは事前情報と装備(ベアスプレーやグループ行動、音で存在を知らせる工夫)で備えましょう。万が一出会ってしまった場合は冷静に距離を取り、追い立てず自治体・警察へ速やかに通報してください。個人での駆除を考える場合は、法令に従い狩猟免許と所定の手続きを経る必要があり、安全と倫理を第一に行動することが求められます。
参考(公式)リンク
- クマ類出没対応マニュアル(環境省) — 対策の公式マニュアル。env.go.jp
- クマに関する各種情報・取組(環境省) — 出没情報、報告体制等。env.go.jp
- 東京都:ツキノワグマ被害防止(実践的対処法の例) — 具体的な遭遇時の対処がわかりやすい。kankyo.metro.tokyo.lg.jp
- 狩猟免許を取得する(環境省・狩猟免許案内) — 免許区分・試験の概略。env.go.jp
- 都道府県別問合せ先一覧(環境省) — 免許申請窓口の確認用。